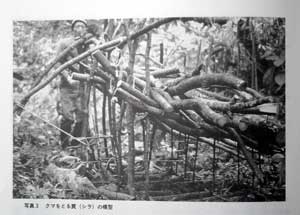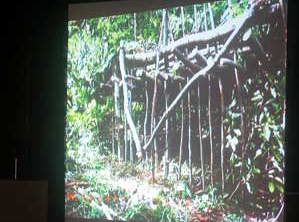キノコ、イワナ、サクラマス、焚き火の材、物を包む材、山菜、木の実、狩猟・マタギの自然知 |
|||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||
| 「白神山地ブナ帯地域における基層文化の生態史的研究」(掛屋誠・弘前大学ほか、平成2年3月)には、実に興味深い記録が記されている。特に目を引くのは、「マタギの自然知の世界」(齋藤宗勝、牧田肇、瀬上景子)・・・これは、西目屋村砂子瀬に住むマタギ・工藤光治氏(当時48歳)の白神の自然に関する知識と利用について聞き書きしたものである。
|
|||||||||||||||||||||||
| キノコに関する自然知 | |||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼ツクシとマイタケ・・・マイタケを採る時は、長さ1m程度のツクシを使う。ブナやイタヤカエデなどの枝のさきをノミのように平に削ったものを「ツクシ」という。マイタケは、木の根の洞穴に生えることが多いが、そんな時マイタケの根の当たりに見当をつけてツクシを差込み、感覚をつかんで株全体を起こして根から壊さず切り取る。こうしないと商品価値がなくなる。 ▼マイタケ以外は刃物で採る・・・金属の刃物を鍛冶屋で作ってもらっている人もいるが、これで採るとウドなどは「ツキル」(次から生えない)と言って、あまり使わない。ただし、キノコ類はツクシを使って採るマイタケ以外は、全て刃物で切り取る。こうすると、水洗いしただけで食べられる。手で引っ張って採ると、生育環境が破壊されて、キノコが生えなくなるからだ。 |
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼良いマイタケを採るには・・・マイタケを採る時は、根株が残らないように綺麗に採る。運悪く育ちすぎて腐ったマイタケを見つけたら、すっかり取り去る。こうしないと、来年その木から良いマイタケが採れない。これは、根株を残しておくと、木がマイタケに栄養をとられ続けるからだと言われる・・・この記述は、今年の赤石川のトンビマイタケの謎が解けたように思う。 | |||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▽考察・・・左は、昨年の8月中旬、ブナの根元に生えていたトンビマイタケの巨大な群れ。ちょうど旬のトンビマイタケであったが、腐るまで栄養をとられ続け、ブナがかなり弱ったに違いない。右は、2005年8月中旬、同じに木に行って見るとトンビマイタケの気配はゼロだった。ちょっと信じ難い光景だった。もし時期がずれていたとしても、昨年のような凄いトンビマイタケは生えなかったのではないか。 そして仙北マタギの戸堀さんの話・・・マイタケは、頻繁に人が入り、毎年採取している場所は、翌年も生える。ところが、お助け小屋より上流部は、ほとんどマイタケ採りをする人がいなくなった。生えてもそのまま腐ってしまうと、翌年から何年も生えなくなる。数年に一度しか豊作にならない。ただし、1カ所見つけると数十キロにも達する・・・キノコも人為を加えないと、毎年良いキノコは生えないとの結論に達してしまうのだが・・・。 |
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼どんなキノコを食べるか・・・目屋の人は木に生えるキノコは食べるが、地面に生えるキノコはあまり食べない。キノコ類の収穫を知るには、山全体の黄葉と庭に植えている木の様子、雨の降り方を見て入山時期を予測する。 | |||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||
| ▼キノコがよく生える斜面・・・山ではシモピラ(西日が当たる斜面)には、キノコが少なく、オモテピラ(東、北斜面)には多い。マイタケは、ミズナラの根につくが、伐根は腐りにくく、伐倒してから30年以上もつく。シログサレをしているような木はマイタケが生える。だから伐根は宝物とする。 ▼商品価値のあるキノコ・・・形の良いキノコは商品価値がある。昔は、ナメコ、シイタケ、ムキタケ、マイタケは、ホウノキの葉に包んで売った。現在は、ほとんどが塩蔵であるが、キクラゲは乾燥保存する。 |
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼利用するキノコ類・・・ブナハリタケ、キクラゲ、ナラタケ、ナラタケモドキ、シイタケ、シメジ類、ナメコ、サクラシメジ、マイタケ、ムキタケ、エノキダケ、ヤマブシタケ
|
|||||||||||||||||||||||
| イワナ、サクラマス | |||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||
| ▼イワナ・・・とる時期は6〜7月一杯で、川にいるシマアブが出るようになると止めた。 ▼マス(サクラマス)・・・ヤスで突いてとる。昔は、暗門→ヤナダキ沢→赤石川二股。ここが不漁であればさらに、ヤナギツクリノ沢→追良瀬川というルートでとりに行った。 |
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼ダンノ・・・イワナを入れるための箱。サワグルミの皮で作り、ヤマブドウの皮でしばった。深さがあって厚みがなく、座布団を二つ折りにしたような形をしている。(写真左:サワグルミの森、右:ヤマブドウ) ▼サンショウ・・・山には自生していない。山でイワナのタタキを作る時、持参した若い果実を混ぜて叩く。 |
|||||||||||||||||||||||
| 焚き火の材・・・ブナ、ダケカンバ、オオバクロモジ | |||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼焚き火・・・ブナは、火を焚くとき一番下に敷いて台とする。山で最もよく使う燃料である。ダケカンバの樹皮は、焚き火の火を起こす焚きつけに使う。山に入る時に取っておいたものを携行する。オオバクロモジは、水をはじくので火を焚く時の焚きつけに使う。春先のベニイタヤは樹液が多く「ナキツライタヤ」と言って燃え難い。(写真左:ブナの風倒木を利用した焚き火、右:ダケカンバ)
|
|||||||||||||||||||||||
| 物を包む材・・・オオバクロモジ、ホオノキ、アキタブキ | |||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼物を包む材・・・葉がついたままのオオバクロモジの枝でツトを作り、採取したマイタケを包んで下山する。昔は、キノコ類をホウノキの葉に包んで売った。大きなアキタブキは、二枚合わせて物を包むのに利用した。(写真左:ホウノキの葉にイワナを包む、右:アキタブキ)
|
|||||||||||||||||||||||
| 山菜に関する自然知 | |||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼山菜の採り方・・・ウドやアザミなどを採る時は、ツクシを使う。ツクシの刃と反対側で土をほじくり、白い根が見えたところで刃を使って切り取る。ワラビ、ゼンマイ、シドケなどは手で折って採る。手で折って折れるところまでは食べられるからである。フキは刃物で切り取る。男はナタ、女はカマを使う。 | |||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼ゼンマイ・・・白神山地では、主に崖縁に生える。急斜面で、落ちないようにしながら採らねばならないので、ゼンマイ採りは最も重労働であり、痩せてしまうと言われる。昔はナワバリがあって、家から日帰りで採る人が10人くらい、山泊りする人も10人くらいいた。山では、採ったゼンマイの綿を取り除き、茹でてから重さ1/10程度になるまでサワグルミの皮に広げて天日で干した。 この乾燥は3日でできれば早いほうであった。家に帰ってから、さらに茎の堅い部分を切除するなど再調整をしてから売り渡した。色出しをする時は、銅を入れて茹でる。ゼンマイは、自分の家で食べるものではなかった。干したものは売り渡し、塩蔵したものは歳暮用とした。 |
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼アザミ類(写真左)・・・春、一番に出る山菜。30cm程度まで伸びたものを採る。天ぷらや味噌汁に合い、おひたしにもする。春のクマ鍋には最も合う山菜である。40〜50cmに伸びたものをシンポと言い、手で折れるものだけを採って茎だけにして皮を剥き、味噌汁や肉鍋などにするとよい。 ▼アキタブキ(写真右)・・・春、10〜15cmに伸びたら食べる。太いものは、茎の穴に身欠ニシンを詰めて煮込む。この方が別々に煮たものよりも美味い。フキノトウは、飢饉の時でも食べなかったが、今は伸びて大きくなった花茎を食べる。 |
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼アイコ(ミヤマイラクサ(写真左))・・・葉を取り除き、茎だけ持ち帰って塩蔵する。胡麻和えやおひたし、さっと茹でて酢醤油で食べる。採ってきたものをそのまま折って味噌汁に入れて食べることもある。皮を剥かねばならないので手間がかかる。 ▼シドケ(モミジガサ(写真右))・・・天ぷらやおひたし、味噌汁などにする。アザミ類と同様に塩蔵したものは水洗いして味噌汁の具として食べると、春の生のものより上等である。 ▼ボンナ(ヨブスマソウ)・・・おひたしや味噌汁、胡麻和えなどにする。塩蔵する。 |
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼ウド(写真左)・・・ツクシで採り、塩蔵する。 ▼カタクリ(写真右)・・・葉は食べる。昔は、花が終わった6月頃、大豆を植えるため山の畑の土起こしをすると、球根が出てきたので、これを採ってきて食べた。 |
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼リュウキンカ(写真左)・・・流れのある湿地に生えている。山では見つければ必ず採ってきて食べる。おひたしが美味い。 ▼ワサビ(写真右)・・・昔は根だけを粕味噌に漬けて食用とし、茎と葉は捨てていた。山では酢味噌に漬けたりもする。現在は、茎葉とも食用とする。 ▼ワラビ・・・塩蔵するか、茹でてから干して保存する。歳暮用や自家用として消費した。昔は、根から澱粉を取り餅にした。 |
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼ニリンソウ(写真左)・・・おひたしや味噌汁などにするが、一度に多く食べない。日本海側の大間越に多く見られるが、岩崎一帯では食べないという。 ▼ミズ(ウワバミソウ(写真右:ミズのムカゴ))・・・塩蔵して食べる。ムカゴ(玉)も食べる。 |
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼エンレイソウ(写真左)・・・果実(秋)を食べる。山菜採りに行った時、あれば必ず採る。堅めの果実は、採ってきて米ぬかの中に入れて柔らかに熟させてから食べた。 ▼コゴミ(クサソテツ(写真右))・・・おひたしや味噌汁、胡麻和えなどにする。塩蔵する。 |
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼ダイモンジソウ(写真左)・・・春にクマ狩りに行った際、食べ物に変化を求めて味噌汁にしたり、酢の物にして食べるが、しょっちゅう食べることはしない。 ▼チマキザサ、タケノコ(写真右)・・・道路端などに生えており、春一番に出る細い若芽を食べる。細いので味がよく沁み込む。チシマザサの若芽(タケノコ)も食べる。 |
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼トリアシショウマ(写真左)・・・茹でてから干して保存食品とした。 ▼ギョウジャニンニク(写真右)・・・目屋の方にはないが、日本海側の大間越に多くある。最近、採ってきて食べるようになった。 |
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼オオバユリ(写真左)・・・鱗片を一枚づつはがして食べる。昔は、茹でて食べたが、今は天ぷらにして食べる。 ▼オオイタドリ(写真右)・・・さっと茹でて酢味噌で和え、これにタラの干物などを混ぜて食べる。味噌汁にも入れる。塩蔵したものは煮付けにする。 ▼アカソ・・・茹でてから乾燥して保存し、和え物や味噌汁としたが、筋っぽいので今はほとんど食べない。 ▼タチギボウシ・・・味噌汁やおひたしなどにして食べる。 ▼シオデ・・・そのまま食べた方がよい。余った時はワラビとともに塩蔵した。 ▼ツルニンジン・・・生の根に味噌をつけて食べたり、味噌漬けにして食べる。生で食べると臭いは強いが甘味がある。 |
|||||||||||||||||||||||
| 木の実・その他 | |||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼アケビ(写真左上)・・・果実は果肉と果皮の両方とも食べるが、果肉はしゃぶる程度。果皮は、味噌田楽や空揚げにする。昔は、果皮を干して保存食品とした。そのため、女の人たちが採りに歩いた。この乾燥品は、戻して煮付けて食べた。 ▼ツノハシバミ(写真左下)・・・秋に果実を生で食べる。 ▼ブナの実(写真右)・・・昔は、拾い集めてきて食べたが、今は退屈しのぎに食べる程度。 |
|||||||||||||||||||||||
 |
 |
||||||||||||||||||||||
| ▼ヤマブドウ(写真左)・・・果実をジュースにした。今は、ジャムや果汁入りの寒天をつくる。果実酒にもする。 ▼トチノキ(写真右)・・・里では食用とすることはなかったが、マタギに行って雨で小屋に閉じ込められた時、暇つぶしに食べた。 ▼クリ・・・目屋では果実を得ることを重視するので余り切らない。大切にしているので、他人のクリを取ってはいけないし、枝を折ってもいけない。売らずに全て自家消費した。 ▼クルミ・・・果実を集めるのは女性の仕事で、秋、二百十日を過ぎると拾いに歩くことが日課であった。里山に多くあったので植えることはしなかった。 ▼オオバクロモジ・・・小枝を土瓶で煎じて茶の代わりとして飲んだ。 ▼コクワ・・・果実が美味いので見つければ採る。果実酒にもする。 ▼マタタビ・・・黄色く熟した果実を食べる。 ▼イチゴ類・・・ほとんどの種類の野イチゴを食べる。 ▼ホドイモ・・・昔は、よく塊根を掘ってきてストーブの上で焼いて食べた。ジャガイモやサツマイモの中間のような味がする。 ▼ヤシャビシャク・・・果実を食べる。 |
|||||||||||||||||||||||
| 狩猟及びマタギの自然知 | |||||||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 参考文献 | |||||||||||||||||||||||
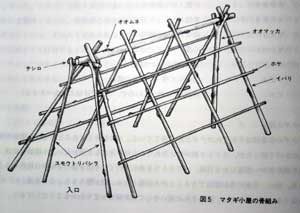 雪が積もると、水場が分からなくなるので、秋のうちに囲いをして雪が積もっても分かるようにしておく。
雪が積もると、水場が分からなくなるので、秋のうちに囲いをして雪が積もっても分かるようにしておく。